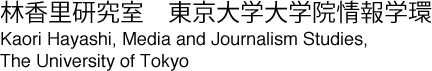News
矢口祐人編『東大塾 現代アメリカ講義 トランプのアメリカを読む』東京大学出版会 に一章を書きました。
「トランプ時代の米国メディア SNSの普及と伝統的ジャーナリズムの行方」矢口祐人編『東大塾 現代アメリカ講義 トランプのアメリカを読む』東京大学出版会、2020年、126-155頁。を発表しました。
東京大学 Beyond AI 研究推進機構 「B’AI」を開始します
東京⼤学 Beyond AI 研究推進機構
B’AI Global Forum Project
(ビー・エイアイ グローバル・フォーラム プロジェクト)
― AI時代における真のジェンダー平等社会の実現とマイノリティの権利保障のための規範・倫理・
実践研究 ―
B’AI Global Forum Project チーム
プロジェクトリーダー:林⾹⾥ 東京⼤学⼤学院情報学環教授
副プロジェクトリーダー:板津⽊綿⼦ 東京⼤学⼤学院総合⽂化研究科准教授
事務局⻑:⽮⼝祐⼈ 東京⼤学⼤学院情報学環教授
B’AI Global Forum Project 概要
このB’AI Global Forum Project は、ジェンダー平等社会とマイノリティの権利保障という社会⽬標を、AI が
社会のあらゆる局⾯に浸透する時代に、いかによりよく実現していくかを主眼として構想しています。
現代、経済格差やジェンダーや⼈種/⺠族などに基づく差別が⽌む気配はなく、課題は⼭積しています。とりわけ、2020 年新型コロナウイルスの感染拡⼤以降、政治、経済、⽂化など社会の活動において、デジタル技術を利⽤したコミュニケーションの⽐重が格段に増す中、経済格差やジェンダー、⼈種/⺠族などに基づく差別は、⼀層助⻑されていく例が世界各地で報告されています。
このプロジェクトでは、こうした社会問題の克服を⽬指し、市場原理ならびに⼀⽅的な科学技術の発達を最優先させてきた近代の諸制度や価値観を根本から問い直し、現状の社会の諸制度や組織構造の成り⽴ちを解明していく知的な作業を推進していきます。
さらに、AI などの先端技術が、あらゆる⼈の⽣に貢献する技術となるよう、多様な分野からの研究者、実務家、ジャーナリスト、市⺠たちとともに、現状の課題を⾒出し、その解決を模索、提案していきます。
B’AI Global Forum Project の2つの⽬標
具体的には、B’AI Global Forum Project では、
1)AI をはじめとするデジタル情報技術と社会の関係を反省的かつ批判的に解明すること
2)⾔論・表現空間の公正性を実現すること
をプロジェクト推進の2つの⽬標としています。
B’AI Global Forum Project の4 つのテーマ
私たちは、このプロジェクトを「B’AI Global Forum Project」と名付けました。この「B’」には、AI 以前の⾔論・表現空間の歴史(before)、AI 発展の背後の利害(behind)、下部構造(beneath)など、AI 等の技術を取り巻
く歴史やそれを⽀える社会構造を多⾓的に考察していこうという意味が込められています。
プロジェクトは、以下の4 つのテーマを中⼼に推進していきます。
1)AI をはじめ、デジタル情報技術による⼥性やマイノリティへの差別・暴⼒の解明
2)AI をはじめ、デジタル情報技術による多様かつインクルーシヴなメディア表現空間の設計
3)若⼿研究者、起業家、実務家、その他⼀般市⺠とともにAI 等の技術をめぐる課題を討議する⽂理融合グローバル・フォーラムの創設
4)デジタル情報化時代の倫理の再考、およびそれに基づくインクルーシヴ
教育の実践みなさんも私たちと、このB’AI Global Forum Project で、AI とともに⽣きる未来について考えませんか。
論文「「実名か匿名化か」の問いの罠 個人化する市民感覚との乖離」を発表しました。
論文「「実名か匿名化か」の問いの罠 個人化する市民感覚との乖離」を発表しました。『Journalism』2020年7月号 朝日新聞社、58-65頁。
NHK Online “Black Lives Matter が意味するもの”にコメントしました
NHK Online “Black Lives Matterが意味するもの” にコメントしました。
6/24 (水)5時半からオープン・ゼミを行います
6/24(水)午後5時半からオープンゼミをする予定です。
・日時:2020年6月24日(水)17:30-19:00
・形式:オンライン開催
・進行:
- 【第1部】基調報告「メディア関係者が大学院で学ぶ意味」 (17:40-18:00)
- 【第2部】グループディスカッション「ここが変だぞ!日本メディア!?」 (18:10-18:30)
- 【第3部】クエスチョンタイム (18:30-18:55)
研究室説明会の参加希望者は6月19日(金)までにこちらからご登録ください。(終了しました)

NHK「せかいま(6月7日放送分)」についてコメントしました(毎日新聞)
NHKの「せかいま」について毎日新聞でコメントしました。
「ステレオタイプの「怒る黒人」、レベル低い歴史認識…NHK、米抗議デモ解説動画を削除、謝罪」(毎日新聞6月9日)
「林香里・東京大教授(ジャーナリズム研究)は、そもそも「放映された番組自体に違和感があった」と指摘する。番組では黒人男性が白人警察官に殺された事件などを説明した上で、背景の解説としてアニメ動画を使用していた。しかし、ツイッターの投稿内容と同様に「銃社会のアメリカで白人警官は黒人への恐怖の中で仕事をしている」と、まるで「黒人=暴力」とするかのような説明やデモの「暴徒化」という側面を強調していた。林教授は「銃を持つのは黒人だけではないし、デモのほとんどは憲法に保障された抗議活動だ。NHKは米国をこれほど理解していないのかと衝撃を受けた」と話す。
アニメ動画の描き方についても「『怒る黒人』はステレオタイプ(固定観念)だ。こうした描き方が偏見を助長する。黒人差別の長い歴史を十分に説明せず、あまりにもレベルが低い」と指摘する。
さらに林教授が危惧するのは、番組に出演していた米国駐在の記者ら、国際報道を担うNHKの局員が総動員で携わっていたにもかかわらず、こうした放送がなされたことだ。「世界各地で問題提起されているテーマなのにあまりに理解が浅い。日本と無関係な『対岸の火事』と思っているのではないか。日本の国内にもさまざまな差別があり、大規模デモは起きなくても苦しんでいる人はたくさんいる。人ごとのような報道はジャーナリスト失格です」と憤る。「このような番組はいったん中止し、こうした内容のどこに問題があるのかを徹底的に検証すべきだ」
学者の会 × ChooseLifeProjectコラボ企画オンラインシンポジウム 「2020年のナショナリズム」でお話しました
学者の会 × ChooseLifeProjectコラボ企画オンラインシンポジウム「2020年のナショナリズム」でお話しました。タイトル「日本のメディアのナショナリズムはどこから来るのか」と題して、その特徴を「高い、古い、デカい」と説明しました。
Our new paper on incidental news consumption is out
Our new paper on incidental news consumption was just published on “Journalism”.
Mitchelstein, Eugenia, Pablo J Boczkowski, Keren Tenenboim-Weinblatt, Kaori Hayashi, Mikko Villi, and Neta Kligler-Vilenchik. “Incidentality on a continuum: A comparative conceptualization of incidental news consumption.” Journalism.