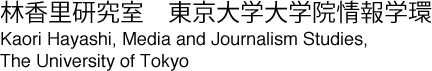News
Our new paper on incidental news consumption is out
Our new paper on incidental news consumption was just published on “Journalism”.
Mitchelstein, Eugenia, Pablo J Boczkowski, Keren Tenenboim-Weinblatt, Kaori Hayashi, Mikko Villi, and Neta Kligler-Vilenchik. “Incidentality on a continuum: A comparative conceptualization of incidental news consumption.” Journalism.
延期になりました→『足どか』刊行記念ブックトークを開催します
残念ながら、このブックトークは延期となりました。スケジュールが決まったら再度お知らせいたします。
===============
『足をどかしてくれませんか。』(亜紀書房)刊行記念イベント 「韓国と日本――フェミニズムの伝えかた、論じかた」を開催します。
日 時:2019年3月17日(火)開場18:30/開演19:00
会 場:Readin’Writin’ BOOKSTORE(東京メトロ銀座線田原駅徒歩2分)
参加費:1000円
ご参加をご希望の方は、お名前、連絡先を明記のうえ、readinwritin@gmail.comまでお願いします。
詳しくは こちら
My chapter in a new book on the Liberal International Order.
My chapter in a new book.
“The Silent Public in a Liberal State: Challenges for Japan’s Journalism in the Age of the Internet.” In. The Crisis of Liberal Internationalism. Japan and the World Order. Edited by Yoichi Funabashi and G. John Ikenberry. Brookings Institution Press. Washington. D.C. pp. 325-358.
カテリナさんイムさんチームがNTTデータ特別賞を受賞!
林香里研究室のカテリナ・カシアネンコさんと林東佑(イム・ドンウ)さんが2019年12月18日に開催された第2回NTTデータ-Twitter Innovation ContestでNTTデータ特別賞を受賞されました。情報サイエンス系のコンテストに、林香里研究室のメンバーが受賞の快挙です。おめでとうございます!
林香里編『足をどかしてくれませんか。——メディアは女たちの声を届けているか』を出版しました!
林香里編『足をどかしてくれませんか。——メディアは女たちの声を届けているか』(亜紀書房, 2019年)を出版しました。
12/2「就活セクハラ」の会見をしました
12/2 「就活セクハラ」について、厚労省記者クラブ、ならびに日本外国特派員協会(FCCJ)で記者会見をしました。多くのメディアに取り上げていただきました。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5de4bfbbe4b0913e6f81512a
https://www.businessinsider.jp/post-203450
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201912/CK2019120302000142.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/03/national/japanese-students-push-end-sexual-harassment-job-hunters/#.Xej5quSP61s
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/12/04/editorials/stop-sexual-harassment-female-job-seekers/#.Xej5xeSP61s
https://jp.reuters.com/article/us-japan-sexualassault-students/japan-activists-push-to-halt-sexual-harassment-of-job-seeking-students-idUSKBN1Y60TZ
ほか
「就活セクハラ」根絶に向けて、学生ネットワーク”SAY”から声明を出しました
いわゆる「就活セクハラ」根絶に向けて学生ネットワーク”SAY”から声明を出しました。
「実効性ある「就活セクハラ」対策を求める大学生からの緊急声明」
WAN(Women’s Action Network)のサイトに掲載していただきました。
就活セクハラの実態については、https://www.businessinsider.jp/post-185252
などをご覧ください。
なお、SAY はジェンダーに基づく暴力についての勉強会で、東京都内の大学の学生団体及び学生有志、教員がつながるネットワークです。教員はSAYのメンバーとして、上智大学法学部教授三浦まり先生と”SAYFT (セイフティー)”という大学間グループを立ち上げ、東京大学からは、大学院総合文化研究科板津木綿子先生、東京大学大学院情報学環/総合文化研究科矢口祐人先生たちほかが入っておられます。
内閣府主催 12/1(日)シンポジウム「アジア・太平洋地域 輝く女性たちのHasshin! ~メディアが創る新しい時代~」の開催のお知らせ
内閣府では、アジア・太平洋地域と日本のメディア業界において活躍する女性記者を招聘し、シンポジウムを開催します。
本シンポジウムは、女性記者に焦点を当て、自身が報道してきた記事の紹介や経験談を通して仕事のやりがいを聞くとともに、各国のメディア業界における女性のさらなる活躍に向けた課題などを、共に考えていただくプログラムとなっております。タイトルのHasshin!には、女性記者による記事や報道の「発信」と、女性記者や参加者がキャリアアップ、女性活躍を推進する主体として「発進」することの意味が込められています。
女性記者と参加者とのグループディスカッションや懇親会も予定しておりますので、奮ってご参加ください。
日時:令和元年12月1日(日)13:00~18:00(開場12:30)
場所:京王プラザホテル 5階エミネンスホール(東京都新宿区西新宿2-2-1)
参加費:無料
プログラム:
13:00~13:15 主催者あいさつ
13:15~15:00 パネルディスカッション
モデレーター:林香里氏(東京大学大学院情報学環 教授)
パネリスト:治部れんげ氏(フリージャーナリスト、東京大学大学院情報学環 客員研究員)
武田耕太氏(朝日新聞 科学医療部記者)
久米井彩子氏(NHK日本放送協会 報道局国際部記者)
クエック・エン・ラン・オードリー氏、シンガポール(ストレーツ・タイムズ紙 編集部 国際担当論説部長)
トゥイ・グエン・トゥー氏、ベトナム(ベトナム女性新聞 経済ニュース部 経済ニュース副部長/編集補佐)
15:20~16:30 各国の女性記者と参加者によるグループディスカッション
16:30~16:50 クロージング
17:00~18:00 参加者全員による交流会
申込締切:令和元年11月25日(月)
申込方法:内閣府HP(http://www.gender.go.jp/public/event/2019/011201.html)よりお申込みください。
主催:内閣府
問い合わせ先:本シンポジウムの運営について、内閣府から㈱日本旅行(convention_itd@nta.co.jp)へ委託していますので、こちらにお問い合わせください。
国際交流基金招へい研究員・中央民族大学・王斌(オウヒン)副教授講演会 開催
講演内容
中国新疆ウィグル族自治区のマスメディア事業の発展はこれまで広く注目を集めてきました。本講座では、メディア・エコロジー研究の観点から、中国の各レベルの政府が同自治区のマスメディア事業を進める過程において、その制度設計、実施の経緯、成果と不十分な点等を整理します。新疆マスメディア事業について、できる限り客観的で学術的な視点からお伝えします。
講演者
王 斌 (オウ ヒン)
中央民族大新聞與伝播学院 副教授
司会
林香里
東京大学大学院情報学環教授
日時:2019年11月20日(水)18:00-19:30
場所:東京大学本郷キャンパス 学際情報学府本館6階教室
使用言語:中国語(日本語通訳あり)
参加費:無料
事前申し込み:不要
問い合わせ:「メディア研究のつどい」東京大学大学院情報学環・学際情報学府 林香里研究室 peiya19941023@outlook.com